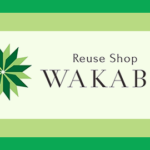ヤフオク!やメルカリなど、フリマアプリは便利ですよね。
いらなくなった物が処分できるし、ちょっとしたお小遣いにもなる。まさに一石二鳥とはこのこと。
副業として利用している人も多いのではないでしょうか。
しかし、転売には古物商許可証が必要な場合があります。知らず知らずのうちに法律を破っているかもしれません。
ある日突然、警察から連絡がくる…なんてことは避けたいですよね。
今回は、フリマアプリに出品する際に古物商許可証が必要になる条件をご紹介します。
これを読めば、安心して出品できますよ!
古物商許可証が必要になる条件は3つ!違反すると…

フリマアプリに出品する際に、古物商許可証が必要になる条件は3つです。
- 古物営業法が定める「古物」を取り扱う
- 営利目的で販売している
- 繰り返し販売している
無許可で転売した場合、古物営業法の「無許可営業」にあたり、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金になる可能性があります。
実際に無許可で古着の転売を行ったとして、書類送検になったケースもありますよ。
古物営業法が定める「古物」を取り扱う
古物営業法では、古物を以下の通り定義しています。
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
いわゆる「中古品」「新古品」が該当します。
これらの物を売るときに、許可証が必要になるんですね。
しかもパーツや修理品でも必要になるんだそう。
中古品でも自分が使用して不要になった物を片付けるときは、古物でも販売できます。
そのままフリマアプリに出品できるので、安心してくださいね。
さらに「お店で買った新品」も許可なしで販売できます。
いわゆる「転売ヤー」が違反にならないのは、新商品を転売しているからなんですね…。
他の法律で制限がかけられている場合もあるので、確認してから出品しましょう。

営利目的で販売している
儲けることを目的に中古品を出品するなら、古物商許可証が必要です。
例えば、リサイクルショップをはしごして古本を買い集め、フリマアプリに出品した場合。
「仕入れ」に当たる行動があれば、営利目的と見なされる可能性が高まります。
さらに、全く同じ商品を大量に出品していたり、高額で出品している場合にも疑われやすくなります。
逆に、利益を得ることが目的でなければ、無許可でも問題ありません。
例えばリサイクルショップで買ったけど、もう読まない本。不用品を処分することが目的なので、そのまま出品できます。
繰り返し販売している
「反復継続」とも言われます。
長期間にわたって転売を繰り返していると、営利目的であるとみなされます。
確かに、何度も同じ物が出品されていたら、「いらない物を処分しています」なんて信じられませんよね…。
同じ物でなくても、継続して中古品を出品していると、無許可営業のリスクが高まります。
例えば、中古家電を定期的に仕入れて販売したり、絶版した本を集めて繰り返し売っている場合です。
転売を反復継続して行うなら、許可証を申請しましょう!
ただし繰り返しになりますが、これが営利目的でなければ問題ありません。
不安になるなら、取得してしまうのもアリ!
フリマアプリに中古品を出品するときに、古物商許可証が必要になる条件をご紹介しました。
「古物を営利目的で、繰り返し販売している」ことがポイントです。
とはいえ、具体的な数字があるわけではないんです。
一応、消費者庁が出したガイドラインで、販売業者に該当する基準が定められています。
しかし、「この基準を上回らなければセーフ」というわけではありません。
しばらく転売を続けるつもりなら、思い切って古物商許可証を取ってしまうことをおすすめします。
一度取得すれば、更新手続きナシで一生使えます。
さらに「古物市場」と呼ばれる古物商専門のオークション会場に入ることもできますよ!
手数料などで2万円ほどの出費が発生しますが、摘発されるリスクを避けられるなら安いものではないでしょうか。

まとめ
不用品を処分するためなら、中古品でもフリマアプリに出品できます。
しかし、ビジネスとして中古品を出品するなら、古物商の許可が必要です。
違反した場合、3年以下の懲役か100万円以下の罰金、もしくはその両方が課せられるかもしれません。
実際は書類送検になるケースが多いようですが、今後厳しくなる可能性もあります。
「警察に摘発されるかもしれない…」と怯えながら転売するくらいなら、古物商許可証を手にいれて、堂々とビジネスしてみませんか?

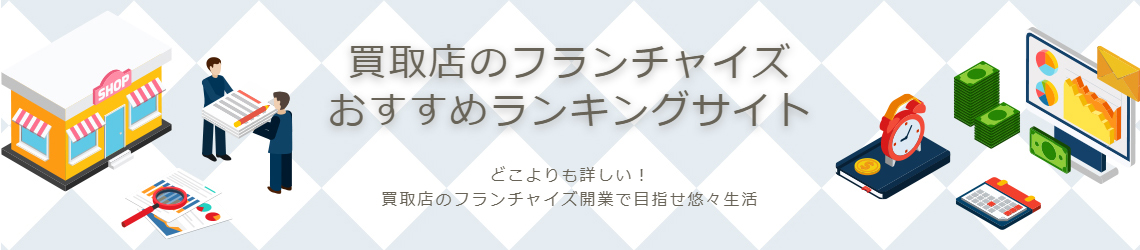













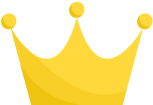 ブランド横須賀 独立開業支援
ブランド横須賀 独立開業支援 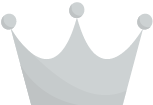 WAKABA(わかば)
WAKABA(わかば) 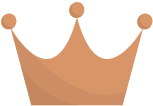 買取専門リサイクルマート
買取専門リサイクルマート  ブランド横須賀 独立開業支援
ブランド横須賀 独立開業支援  WAKABA(わかば)
WAKABA(わかば)  大黒屋
大黒屋