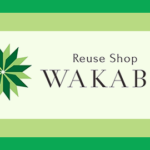古物商の許可申請には、いくつかの書類が必要です。略歴書は記入する部分が多く、書き方に戸惑う方も少なくありません。
警察が公開しているサンプルだけで解決できず、悩んでいませんか?
この記事では、略歴書に書くべき内容や、実際の記入例などを紹介します。
「自分の経歴の場合、どう書けばいいか分からない!」という方に、おすすめです。
古物商の略歴書とは?

略歴書とは、申請者の過去5年間の経歴をまとめたものです。
「履歴書によく似ている」とも言われます。履歴書との違いは、自己PRや5年以上昔の経歴がいらないことです。
そのため書き込む内容が少なく、空白が目立って心配になるかもしれません。
まずは略歴書がなぜ必要なのか、具体的にどのようなことを書き込むのかを解説します。
略歴書が必要な理由
古物商の許可は、申請すれば誰でも取得できるわけではありません。そもそも古物商が許可制なのは、盗品の売買や流通を防ぐためです。犯罪を犯す可能性がある人には、残念ながら資格は与えられません。そこで、警察署(公安委員会)が、申請者が罪を犯すような人間ではないかどうか審査します。
略歴書は、申請者が犯罪を犯す可能性があるかどうかを確かめるために使われます。特に、「欠格事由」に該当していないかをチェックしているそうです。
古物商には該当してはいけない条件が複数あり、欠格事由と呼ばれています。欠格事由に該当していると申請者の性格に問題がなくても、古物商の許可を与えられません。普通に社会生活を送っていれば、欠格事由に該当することはまずありません。
しかし中には、犯罪目的で古物商許可証を手に入れようとする人もいるため、申請者の経歴は念入りに審査されます。
犯罪を犯す可能性がないことと、欠格事由に該当していないことの2つが伝わればいいので、履歴書のような自己PRは必要ありません。
それよりも、過去5年間の経歴を正直に記入することが重要です。
略歴書に書き込む内容
略歴書に書き込む内容は、地域によって異なります。自身の経歴だけでなく、住所に関する経歴を記入する地域もあるそうですよ。
全国的に共通している項目は以下の通りです。
- 過去5年間の経歴
具体的には、申請日から5年前までの経歴を記入します。 - 賞罰の有無
犯罪歴の有無のことです。 - 氏名住所
- 略歴書の作成日
- 申請する公安委員会の名前
記載方法についても、地域ごとに異なる方法で要求されます。作成する前に、警察署に確認しておくことをおすすめします。
略歴書が必要になる人
略歴書は、古物ビジネスに関わる人全員が用意します。一方で、雇用するアルバイトやパート、正社員などの分は不要です。
個人事業主として申請するか、法人として申請するかで、必要になる人が変わるので、それぞれまとめました。
個人事業主として申請する場合
- 申請者
- 営業所の管理者
法人として申請する場合
- 監査役含む役員全員(非常勤の役員も含みます)
- 営業所の管理者
「管理者」とは、営業所を管理する責任者のことです。古物ビジネスがきちんと行われているかを確認し、警察との対応窓口にもなる重要な役割があります。管理者にも該当してはいけない条件があるので、略歴書の提出が求められます。

略歴書の書き方と注意点

略歴書が必要な理由を紹介しました。
ここからは略歴書の書き方を順番に紹介します。必ずしもこの順番でなくても良いのですが、スムーズに作成できるのでおすすめです。
気を付けるべきポイントも解説しているので、参考にしてください。
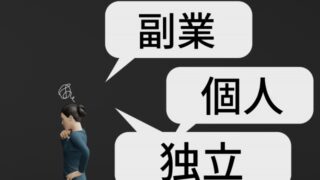
まずは住民票を用意
略歴書を作成する前に、住民票を取得しておくことをおすすめします。略歴書には、住民票から書き写さないといけない情報があるからです。
古物商の許可を申請する際、本籍地記載の住民票も提出します。取得に時間がかかる場合もあるため、先に用意しておいた方がスムーズに準備できます。
近年、住民票をコンビニで取得できる地域も増えています。本籍地以外の住所に住んでいても対応できる場合もあるので、確認してみてください。

略歴書を用意する
略歴書には決まった書き方はありませんが、心証が悪くなる可能性があります。略歴書の作成は、警察署が用意したテンプレートを使用するのが一般的です。
個人的には、警察署を訪れて直接もらう方法がおすすめです。担当者から直接もらうと、ありがちな記入ミスや、審査に通りやすくなるコツなどを教えてもらえます。調べても分からなかったことを確認できるので、不安解消にも役立ちます。
書類をもらいに行くときは、事前に予約を取っておきましょう。
手続きに詳しい方が、常にいるとは限りません。地域によっては、不慣れな警察官しかおらず、手続きに手間取ってしまう可能性があります。
事前に予約を入れておけば、担当者が準備してくれるので、スムーズに申請できます。
経歴をまとめる
申請日から5年前までの経歴をまとめます。上の欄から、古い順に記入してください。
5年前の時点で、会社に勤めている方がほとんどではないでしょうか。その場合、企業に入社した年月から書き始めます。
5年前の時点で学生だった場合は、最終学歴を記入します。
基本的な記入方法は、履歴書と同じです。履歴書の場合、在籍中にどのような業務を担当したのかをまとめますが、略歴書の場合は必要ありません。
業務内容については、手続き中に質問されるケースがあります。
西暦か和暦かで悩むかもしれませんが、どちらでも問題ありません。ただし、書類全体で、どちらかに統一しましょう。書類作成日を和暦で書いたなら、経歴も和暦で統一します。
具体的な書き方は、
「平成○年○月 ××会社 入社」「20○○年○月 ××会社 入社」
「平成○年○月 ××会社 退社」「20○○年○月 ○××会社 入社」
上記のような書き方で十分です。
そして最新の経歴まで書き終えたら、「現在に至る」で締めくくります。
犯罪歴があるならそれも書く
少しナイーブな話になってしまいますが、過去5年間の間に犯罪歴があるなら、それも書かないといけません。
地域によっては、懲罰歴の記入を求められる場合があります。そのような経歴がない場合は「なし」と記入します。
警察署に提出する書類なので、ごまかしは効きません。犯罪歴を隠して申請すると、古物営業法違反に触れる可能性があります。包み隠さず記入しましょう。
犯罪歴があるからといって、古物商許可証が取得できないわけではありません。
「欠格事由に該当する罪を犯したが、執行猶予を満了した」「ケンカして罰金刑になった」など、状況次第では審査に通過する可能性があります。
極端ですが、欠格事由にさえ該当していなければ、古物商の営業許可がおりる可能性はあります。繰り返しになりますが、自身の経歴は正直に記入してください。
ちなみに、犯罪に関する欠格事由は、以下の3つの条件が当てはまります。
- 禁固刑以上を受けて出所5年が経過しない者
- 以下の罪を犯し、罰金刑以上を受けて5年が経過しない者
窃盗罪・遺失物・占有離脱物横領罪・盗品等有償譲り受け罪・背任罪 - 古物営業法に定める以下の罪を犯した者
無許可営業・許可の不正取得・名義貸し・営業停止命令違反
万が一該当している場合は、5年経つまで開業を諦めるしかありません。取得準備に入る前に、確認しておきましょう。

氏名住所を記入する
ここで書き込む氏名と住所は、必ず住民票に記載されているものを書き写してください。住民票も一緒に提出するため、ごまかすことはできません。
氏名はパソコン入力の場合、押印が必要です。地域によっては手書き以外受け付けていない場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
手書きの署名に押印すれば、どの地域でも問題なく申請できます。不安な方は、手書きで記入しましょう。
近年、押印しなくても受け付けてくれる地域が増えています。しかし、まだ慣れていない担当者もいるため、押印しておいた方が混乱を避けられます。
押印には、シヤチハタは使えません。朱肉の認印を使用してください。
書類の作成日を記入する
略歴書を作成した日付も忘れずに記入しましょう。基本的に、署名欄の近くに記入欄があります。
しかし、この日付にも注意が必要です。
古物商許可の申請書類はすべて、申請日から3か月以内のものを使用する決まりになっています。略歴書の日付もこれに合わせ、申請日から3か月以内にしましょう。これが原因で審査に落ちることは考えにくいのですが、やり直しを求められます。
スムーズに開業するためにも、書類の有効期限には注意してくださいね。
略歴書の記入例【ケース別】
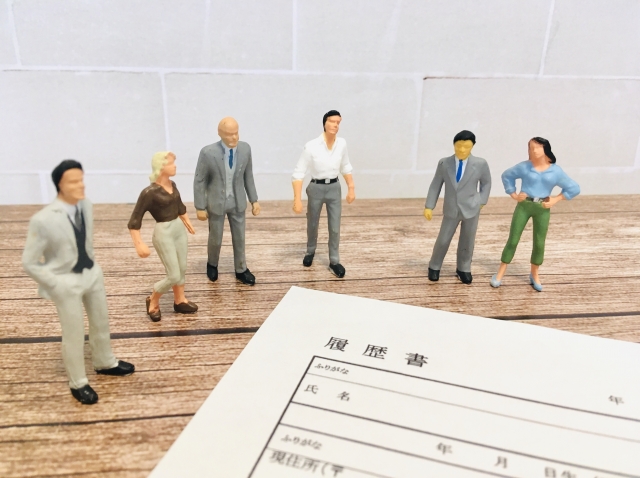
略歴書が必要な理由や、書き方など紹介しました。
とはいえ、実際に書こうとすると、「どう書けばいいの?」と不安になる方もいるかもしれません。
そこで、具体的な記入例をケース別にまとめました。ぜひ、参考にしてください。
5年前は学生だった場合
5年前の時点で就職している企業がある場合、その企業に入社するところから記載します、
一方で、5年前はまだ学生だった場合は、最終学歴から書き始めます。
「平成○年○月 ××学院△△科 卒業」
卒業したその月に、就職が決まっていた場合、同じ枠内にその旨を記載します。書き方の例としては、以下の通りです。
「同月、□□会社に入社」
「同月、□□会社に正社員として入社」
履歴書と同じですね。
無職の期間がある場合
略歴書は、あなたが犯罪に関わってしまう可能性を見るためのものです。無職であることだけで、審査に落ちることはありません。むしろごまかすほうが問題になります。
「結婚して専業主婦になる」「求職活動を開始」と、一言添えれば気分も楽ではないでしょうか。
もし5年以上のブランクがある場合、最後の経歴を記入します。
例えば、以下のように書くことができます。
「平成○年○月 ××会社 親の介護のため退社 現在に至る」
学校を卒業してからずっと無職だった場合は、最終学歴だけ記入します。
「20○○年○月 ××学校□□科 卒業 現在に至る」
無職の期間があっただけで、古物商の許可が下りないということはありません。ただし、手続き中に理由を尋ねられることがあるかもしれません。いざという時に焦らないよう、心の準備だけでもしておきましょう。
フリーターの経歴がある場合
転職時の履歴書では、アルバイトやパートなどは経歴に含まないことがあります。しかし、略歴書の場合は省略せず記入しましょう。
書き方は他の経歴と同じで問題ありません。具体的な書き方の例は、以下の通りです。
「平成○年○月 ××会社□□支店 入社(アルバイト)」
「20○○年○月 ××会社□□支店 アルバイト入社」
余談ですが、派遣社員の経歴の書き方の一例も紹介します。
「平成○年○月 株式会社×× 派遣社員」
「平成○年○月 株式会社×× 入社 派遣社員(派遣先 □□株式会社)」

役員・個人事業主の経歴がある場合
過去5年間に、事業方針を決定する立場にあった方は、それが分かるように記入します。
例えば、役員になったり、個人事業主として開業した場合ですね。
代表取締役や監査役のような役員に就任した場合は、それが分かるように記入します。
具体的な書き方は以下の通りです。
「平成○年○月 ××会社 入社(正社員)」
「平成○年○月 ××会社 代表取締役 就任」
「平成○年○月 ××会社 代表取締役 辞任」
個人事業主として事業を営んでいた場合は、以下の書き方があります。
「平成○年○月 喫茶×× 開業」
「平成○年○月 喫茶×× 廃業」
経歴が多すぎて書き込めない場合
副業していたり、役職が多すぎたりすると、略歴書の枠内に収まらくなります。
その場合、別紙にまとめる方法が良いといわれています。同じ書類をもう一枚用意すると、担当者が混乱するため、あまり好ましくないそうです。また、経歴を省略するのも、担当者の心証を悪くするおそれがあります。
一方で、別紙を用意することに難色を示す担当者がいる可能性もあります。別紙への書き方も含め、警察署や専門家などに問い合わせておくことをおすすめします。
まとめ
略歴書の書き方を紹介しました。
古物商の略歴書は、過去5年間の経歴をまとめたものです。履歴書ほど詳しい経歴を記入する必要がありませんが、空白の期間や虚偽があってはなりません。
書き方が分からない場合、警察署に問い合わせたり、専門家に相談することをおすすめします。地域によって書き方が変わるため、詳しい方に確認した方が失敗しにくくなります。

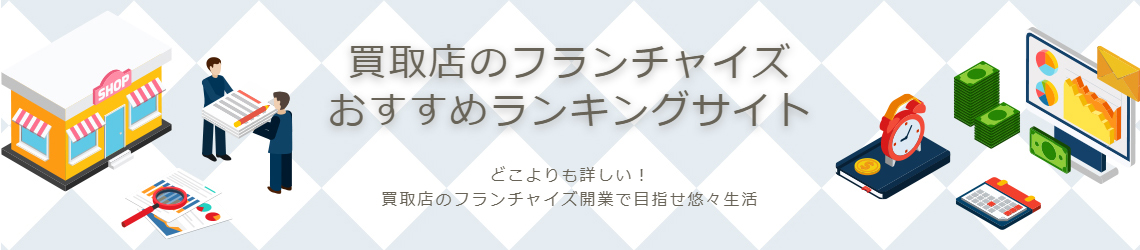










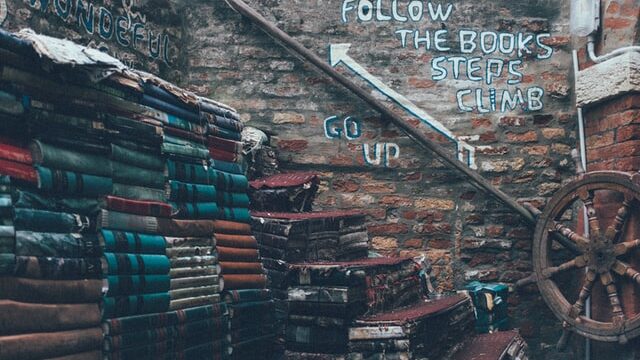

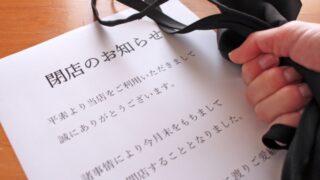
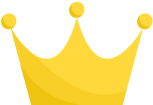 ブランド横須賀 独立開業支援
ブランド横須賀 独立開業支援 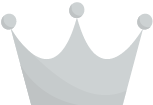 WAKABA(わかば)
WAKABA(わかば) 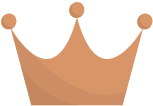 買取専門リサイクルマート
買取専門リサイクルマート  ブランド横須賀 独立開業支援
ブランド横須賀 独立開業支援  WAKABA(わかば)
WAKABA(わかば)  大黒屋
大黒屋