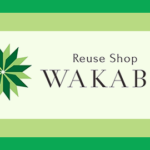脱サラして起業したいなら、何をすれば良いのでしょうか。
まずはどんなビジネスをするのか、事業計画を立てること。
次に資金調達。拠点となる物件を探したり、備品もそろえないといけません。
個人事業主の場合は特に、自分が中心となって進めるため、大変ですよね。
色々と準備を済ませて最後に行うのが税務署などへの手続きです。
でも、どんな手続きをすればいいのか分からない…
今回は、そんな疑問にお答えします!
個人事業主で起業する場合に必要な手続きは?

個人で起業するときの手続きはとても簡単です。
それは「税務署に開業の旨の届け出を行う」だけになります。
開業する住所の管轄の税務署から「個人事業の開業・廃業等届出書」を受け取り、記入して提出するだけで終わりです。
よっぽどではない限り、事業の内容も聞かれることもありません。
また、忙しくて税務署に上記の書類を取りにいけない場合でも大丈夫です。
書類を国税庁のホームページからダウンロードすることも出来ますし、税務署に郵送することも出来ます。
開業してから1か月以内に開業届を提出する
開業するための手続きの書類(個人事業の開業・廃業等届出書)は、開業してから1か月以内に提出するようにしましょう。
1か月を過ぎての提出になってしまうと、個人事業主が受けられる青色申告などの税制上の優遇措置を受けることが出来なくなってしまいます。
提出が遅れるとその年の節税の機会を逃してしまうだけでなく、屋号による銀行口座の開設や補助金、助成金、融資などの利用するタイミングも遅くなってしまうのでくれぐれも注意してください。
必要なもの・費用は?
開業の手続きにかかる費用は「0円」です。
必要なものは以下の通りです。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- マイナンバーカード
マイナンバーカードを持っていない方は以下の通りです。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- マイナンバーが確認できる書類
通知カード、住民業の写し、住民票記載事項証明書などがあります。 - 本人確認書類
運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険証など
また、「個人事業の開業・廃業等届出書」に記載すべき内容は以下の通りですので、事前に把握しておくとスムーズに記載することが出来ます。
- 提出先と日付
- 納税地
- 氏名・生年月日・個人番号・職業
- 届け出の区分
- 所得の種類
- 開業日
- 事業所等を新増設・移転・廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
通常は空欄です。 - 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
青色申告を申し込む場合は申告書を提出するため、「有」に丸をします。 - 事業の概要
- 給与等の支払い状況
1人で起業する場合は「0」と書き、「無」に丸をすると無難です。 - 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
通常は空欄です。 - 給与支払を開始する年月日
通常は空欄です。 - 関与税理士(顧問弁護士がいる場合)
一緒に青色申告の申請も忘れずに!
青色申告とはご存知でしょうか?
青色申告とは確定申告の種類で、他にも白色申告という申告書もあります。
これらの違いは確定申告の控除額が最大で65万円の差があることや赤字を3年間繰り越すことができることです。
仮に開業届と一緒に青色申告書を提出しなかった場合は、白色申告書になってしまいます。
白色申告から青色申告へ変更は出来ますが、変更は次年度までできませんので注意しましょう。
青色申告で確定申告をするのには期限があります。
開業日が1月1日~1月15日の場合は3月15日までに提出。
開業日が1月16日以降なら開業日から2か月以内に提出することが決められています。
開業日によって提出期限が異なりますので注意してください。
青色申告と白色申告とでは、簡易な単式簿記と細かな複式簿記とで作成の手間が大きく異なりますが、控除額が最大で65万円も変わって来るので必要な手間だと思います。
手続きは起業準備の仕上げ作業です!
開業を行うために事業計画を立てたり、場所を決めたり、どんな店にするかを考えたりする必要がありますが、最後の作業が開業手続きです。
開業の手続きが終われば、いよいよお店を開くことが出来ます。
また、開業の届け出である申請書「個人事業の開業・廃業等届出書」は開業してから1か月、青色申告書は開業してから2か月と猶予があります。
うっかりすると忘れてしまうこともありますし、二度手間にもありますのでいっしょに手続きをしてしまいましょう!
最後まで気を引き締めて、詰めが甘かったということがないようにがんばってください!

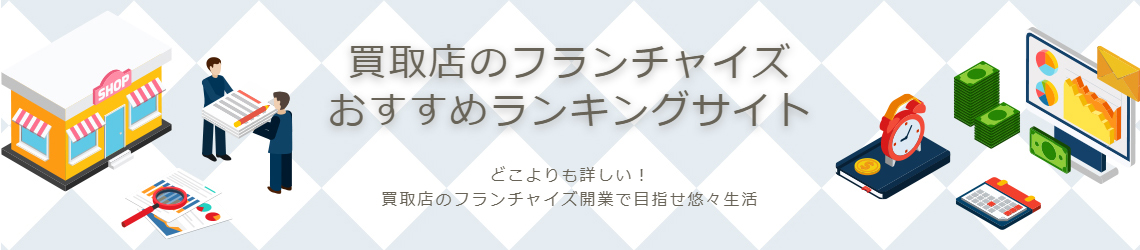




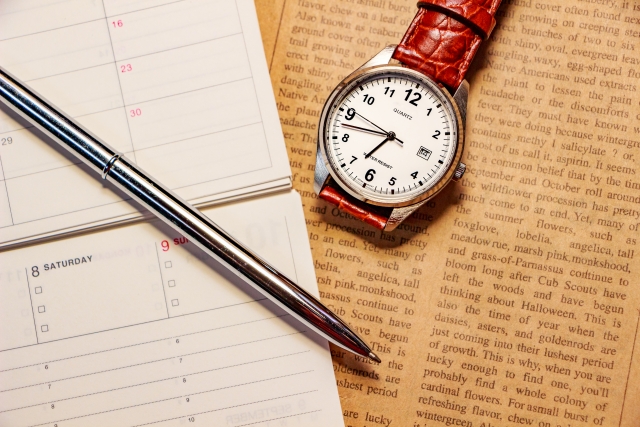








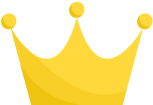 ブランド横須賀 独立開業支援
ブランド横須賀 独立開業支援 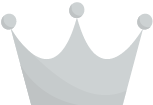 WAKABA(わかば)
WAKABA(わかば) 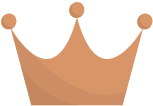 買取専門リサイクルマート
買取専門リサイクルマート  ブランド横須賀 独立開業支援
ブランド横須賀 独立開業支援  WAKABA(わかば)
WAKABA(わかば)  大黒屋
大黒屋