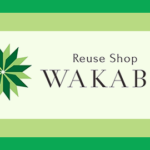開業するための大きな壁のひとつに、開業資金の調達があります。
ビジネスの規模によっては多額の資金が必要で、調達先に頭を抱える方も多いです。
働きながら資金を集めるのには限界があり、時間もかかります。銀行から融資を受けるにも、自己資金をまず用意しなければなりません。
ご家族からの資金援助を考えている方も、多いのではないでしょうか。
しかし、注意しないと、損をするかもしれません。今回は、そんな注意点を詳しくご紹介します。
「親から開業資金を借りる(もらう)予定だけど、何に気を付けたらいい?」
こんな人にオススメです!
親から資金援助してもらう場合の注意点は?

開業資金を用意するときに、ご両親や祖父母からの援助を受けることは一般的ですが、気を付けないと思わぬ請求が生じるかもしれません。
開業資金を親に援助してもらう場合、主な方法は「贈与」と「借入」です。
「贈与」は親から資金をもらう方法で、「借入」は親からお金を借りる方法です。お金を返さなくても良い贈与の方が一見お得に見えますが、金額によっては税金が発生する可能性があります。
ご自身の状況や計画に合わせて、どちらの方法にするか選んでください。
開業資金を親から「贈与」してもらう場合
親から開業資金を受ける場合、贈与税について注意が必要です。
贈与税とは、個人からある程度の財産をもらったときに課される税金です。年間で合計110万円以上の贈与を受け取ると、贈与税は発生します。贈与税は「受け取った贈与額」に対して発生するので、それぞれの贈与額が基準以下でも、贈与税が発生する可能性があります。
例えば、母親から50万円、父親から100万円の資金を受け取ると、合計150万円の贈与になり、課税対象になります。
贈与税の計算方法は以下の通りです。
- 贈与額-110万(基礎控除額)=基礎控除後の課税価格
- 基礎控除後の課税価格×税率-控除額=贈与税
②に当てはめる「税率」と「控除額」は、①で出した「基礎控除後の課税価格」によって変わります。
親からの贈与だと、以下の通りです。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超え | 55% | 400万円 |
参考サイト:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|相続税 |国税庁
先ほどの例に当てはめると、
- 150万-110万=40万
- 40万×10%-0円=4万
したがって、4万円の贈与税が発生します。
贈与額が大きければ、贈与税も高額になります。開業直後の不安定な時期に贈与税を納めること、経営に大打撃を与えかねません。
贈与税を回避する方法はいくつかあります。そのひとつが、年間で受け取る金額を110万円以下にして、分割して受け取る方法です。援助の上限が決まってしまいますが、この方法が一番簡単です。
定期的に繰り返されると、「大きな財産を分割して贈与しているのでは?」と疑いを持たれる可能性があります。繰り返す場合は、贈与の度に贈与契約書を作成して保管しておきましょう。
開業資金を親から「借入」する場合
開業資金を親からか借りる場合、贈与税は発生しません。
贈与税はもらったお金に対する税金なので、返さなければいけない借入金は対象外です。
それでも、贈与税が発生してしまうケースもあります。
よくある例が「親子だから利息(利子)はいらないよ」という場合。
このとき、法的には利息分は親からもらっているとみなされます。利息が年間110万円を超えると、贈与税が発生します。ただ、年間の利息が110万円を超えるような借金はないと思うので、気にしなくても大丈夫そうです。
定期的な返済がない場合も注意が必要です。親子間での貸し借りだと、「お金がたまってからでいいよ」「返済はいいから」といわれるかもしれません。ですが定期的な返済しない借入金は、借入金として認めてもらえません。そうなると、借りた金額がそのまま贈与とみなされます。
いずれにしても、親から開業資金を借りる場合は、借用書や金銭消費貸借契約書などを準備しておく必要があります。そして、その通りに返済するようにしてください。
「開業資金はもらったのではなく、借りている」という証拠を残すことで、贈与税の支払いを回避できます。
追加で金融機関から融資を受ける場合は注意が必要
親からの援助だけでは目標には届かず、金融機関からの融資を検討する方も多いかもしれません。
融資の審査を受けるとき、非常に重要なのが「自己資金」です。自己資金とは、出所の確かな自分の資産のことです。自己資金が多いほど融資の審査に通りやすく、融資可能な金額も多くなる可能性があります。
親からの資金援助を「自己資金」として申告できるケースもあります。
親からの資金援助を「贈与」してもらう場合
親からもらったお金は、自己資金として申告できます。贈与したことを証明するものを提出する必要がありますが、贈与契約書を作成すれば簡単に証明できます。
ただし、開業資金に占める贈与額の割合が大きいと、担当者の心証が悪くなるかもしれません。「自分でお金の管理ができず、返済できないのでは?」と、融資の審査に通りにくくなる可能性があります。
また一時的に自己資金を増やす「見せ金」の疑いを持たれる可能性もあるため、贈与を証明するものを用意しておくことをおすすめします。
親からの資金援助を「借入」した場合
自己資金は自分の資産のことを指すので、借りたお金は自己資金として申告できません。借入金は、あくまで借りているお金であって、自分の資金ではないからです。
万が一、借入したお金を自己資金のように見せかけてしまうと、審査に落ちるリスクが跳ね上がります。自己資金を用意していないのを隠していたと判断され、担当者の信頼を損なう恐れがあります。
自己資金は金額だけではなく、どのように用意したのかも重要視されます。親からの資金援助を自己資金として申告したい場合は、返済義務のない「贈与」の形で受け取りましょう。
開業資金を援助してもらうときにするべきことは?

開業資金を親から援助してもらうとき、必ずやっておきたいことがあります。どのような形で資金援助をしたのかを証明する書類を作っておきましょう。
これにより税務署や金融機関などから疑いを持たれても、説明できる書類があるので安心です。
親からの資金援助を「贈与」として受け取った場合、贈与契約書を作成します。贈与は口約束でも成立しますが、何らかの形で記録を残しておくことが賢明です。
親からの資金援助を「借入」する場合、借用書または金銭消費貸借契約書を必ず作成しましょう。
トラブルを避けるためにやるべきことは、他にもあります。
それぞれ詳しくご紹介します。
贈与の場合
お金を贈与する場合、口約束だけでも問題ありません。
しかし、確定申告は確実に行いましょう。
何らかの形で証拠を残しておきたい方は、「贈与契約書」がおすすめです。贈与契約書を作成すれば贈与を行ったことを証明できるので、無駄なトラブルを避けやすくなります。
例えば、複数回に分けて資金援助を受ける場合、「大きな財産を分割で贈与しているのでは?」と疑いを持たれる可能性があります。援助を受ける度に贈与契約書を作成しておけば、疑いを持たれてもスムーズに説明できます。
贈与契約書の様式や書式は自由ですが、以下の項目は必ず記入しましょう。
- いつ贈与するのか
- 誰が贈与するのか
今回の場合は、親の氏名と住所を記入します。手書きで記入しましょう。 - 誰に贈与するのか
今回の場合は、自分の氏名と住所を記入します。手書きで記入しましょう。 - 何を贈与するのか
金額は具体的な金額を記入します。
手書きで作成する場合、壱、弐、参…といった漢数字(大字)で書きます。 - 贈与する方法
- 契約を締結した日付
贈与する方法は、口座振り込みがおすすめです。贈与した日付を、簡単に証明できます。
また贈与契約書には、贈与する側・される側の署名捺印が必要です。捺印は実印が望ましいとされています。
贈与契約書は、2部作成して、ぞれぞれで保管します。
不安な方は、インターネットからテンプレートをダウンロードする方法がおすすめです。
必要事項を記入、捺印するだけで簡単に作成できます。
借り入れる場合
親からの資金援助を融資として受けとる場合、借用書を作る必要があります。「親子間だから、口約束でいいのでは?」と思うかもしれませんが、贈与を疑われたとき心強い証拠になります。
借用書には、借用書と金銭消費貸借契約書があります。両者の法的な能力に、違いはあまりありません。大きな違いは保管する人です。
借用書は1部のみ作成して、貸主(貸す側)が保管します。金銭消費貸借契約書は、借主(借りる側)と貸主の両方が保管します。家族間の融資なら、借用書が簡単でおすすめです。
借用書を作るのは1部のみですが、誰が作成しても問題ありません。基本的には貸主が作成して、借主が内容を確認してサインしているようです。
借用書には決まった形式はありませんが、以下の項目は必ず記載してください。
- 借用書の作成日
- 貸主の氏名
- 借入金額
壱、弐、参…といった漢数字(大字)で、間隔をつめて書きます。 - 「借主が金銭を受け取った」という内容の言葉
貸主が借主にお金を貸したことを文章で記載します。 - お金を借りた日付
- 返済期日
「令和○年○月○日」のような、具体的な日付を記載します。 - 返済方法
記録が残る口座振り込みがおすすめです。 - 利息
1~5%程度が妥当といわれています。
ここを決めていないと、贈与を疑われる可能性があります。 - 返済が遅れたときの取り決め
遅延損害金などのことです。親子間の場合でも、しっかりと取り決めましょう。 - 借主の住所・氏名・押印
「返済方法」は、具体的に記載しましょう。例えば、銀行振り込みなのか手渡しで返済するか、一括で返済するのか分割で返済するのか…などです。分割払いなら、何回に分けるのか、一回当たりの返済額なども記載します。
ここをあいまいにすると、贈与を疑われる可能性があるため、しっかり記載しましょう。
書類はパソコンで作成しても問題ありませんが、氏名だけは手書きで記入します。改ざんを疑われないようにするためです。
また、貸し借りの金額が1万円以上なら、収入印紙を貼ります。
借用書は基本的に貸主のみが保管しますが、2部作成して借主も保管することをおすすめします。コピーでも問題ありませんが、署名と捺印はそれぞれ手書きで済ませましょう。
借入金の返済は、借用書通りにしましょう!
借入金の返済は、借用書に記載された条件通りに行うことが重要です。
借用書通りに返済しないと、「贈与をごまかそうとしていないか?」と疑われてしまいます。
家族間の取り決めだと甘くなりがちですが、ビジネスのためにお金を借りている事実に変わりはありません。信用をなくさないためにも、緊張感をもって返済しましょう。
同時に、返済が借用書通りに行われていることを記録に残しておくと、安心です。銀行の口座振り込みなら、通帳で返済の記録が分かるので、スムーズに説明できます。
手渡しで返済する場合は、返済の都度領収書を作成しましょう。領収書があれば、必要な場合に証拠として提出できます。
作成した書類は公正証書にしておくと、さらに安心!
作成した書類は、公証役場と呼ばれる場所で「公正証書」にしておくと安心です。
公証役場にいる公証人と呼ばれる人が、書類を法的効力のあるものにしてくれます。法的効力のある契約書があれば、贈与を疑われてもスムーズに説明できます。
また、原本は20年間保管されるので、万が一紛失しても安心です。
公正証書にするためには、数千円から数万円の手数料が必要です。申し込んでから手元に届くまで、2週間程度の時間がかかります。
ここまでやらなくても…という人は公証役場で「確定日付」をもらっておきましょう。
確定日付は「この書類は、この日付に確かに存在していました」という証拠になります。
どちらも公証役場に出向いたり、手数料や印紙代がかかります。
少し痛い出費になるかもしれませんが、トラブル回避のためにも、どちらかはやっておくことをオススメします。
https://www.koshonin.gr.jp/list
まとめ
開業資金を親から援助してもらう場合、「贈与」と「借入」の2つが主流です。
贈与の場合、金額によっては贈与税が発生します。贈与税を払う義務は受け取った側にあるため、気になる方は対策をたてて贈与してもらうか、借入することをおすすめします。
借入の場合、親にお金を返済しなければなりません。きちんと返済していないと「贈与」とみなされ、贈与税が発生する可能性があります。借用書を作成して、その通りに返済しましょう。
どちらにしても、お金の流れが分かるよう、記録に残しておくことが重要です。
お金のやり取りは、一歩間違えると信用問題にかかわります。不備のないように準備して、スムーズに資金を調達しましょう!

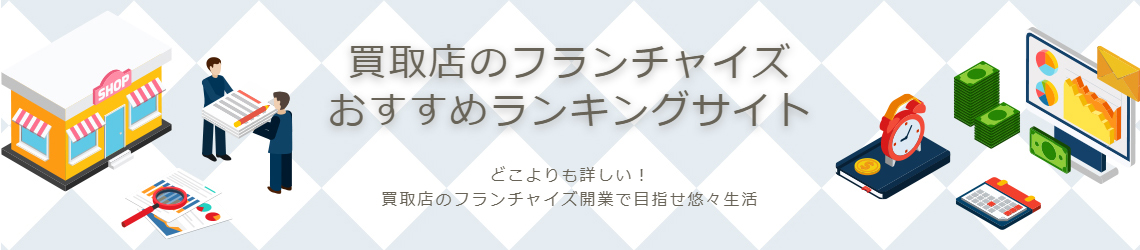




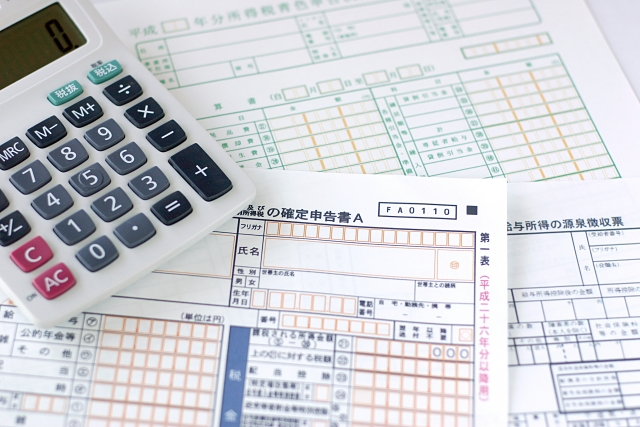








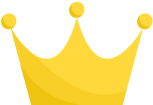 ブランド横須賀 独立開業支援
ブランド横須賀 独立開業支援 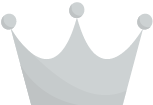 WAKABA(わかば)
WAKABA(わかば) 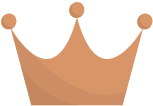 買取専門リサイクルマート
買取専門リサイクルマート  ブランド横須賀 独立開業支援
ブランド横須賀 独立開業支援  WAKABA(わかば)
WAKABA(わかば)  大黒屋
大黒屋